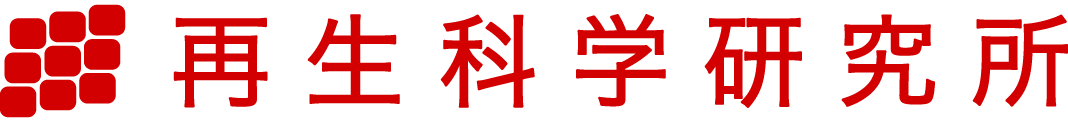
1月末、もしくは2月頃によく「旧正月」という言葉を耳にしますよね。
「旧正月」とは何なのでしょうか。
旧正月とは、旧暦のお正月のことです。
先に旧暦について触れておきます。
旧暦とは、簡単に言うと昔の月日の数え方です。
明治6年(1873年)まで使われていました。
旧暦とは太陽太陰暦のことで、月の満ち欠けを基準にされています。
月の始めは新月、15日が満月となっています。

現在は太陽暦が採用されていて、太陽の動きを基準とした暦です。「旧暦」とは反対で「新暦」といいます。
新月から次の新月までは平均29.5日です。1年間が354日となります。
新暦では1年は365日なので、ずれが生じてしまいます。
日本は1月1日にお祝いをしますが、他のアジアの国では旧正月をお正月としてお祝いされています。
お盆も、地域によって異なりますよね。
旧正月は1月21日から2月20日の間にやってきます。
そのため、2月に海外の観光客が多かったり、一部の地域で祝われていたりするのです。
聞いたことはあるけど、詳しくは知らなかった「旧正月」。
今年の旧正月は1月29日です。
皆さんも旧正月を調べてみて、日本とは少し違うお正月を知ってみてはいかがでしょうか。